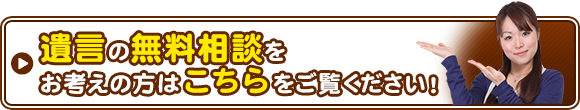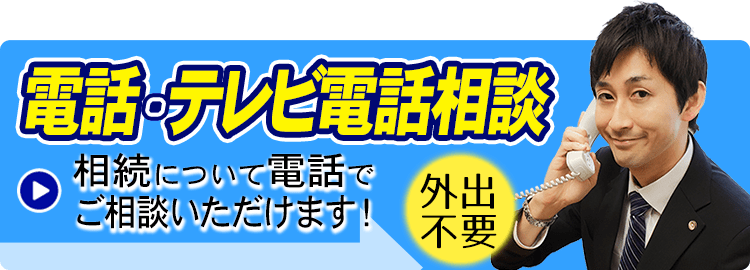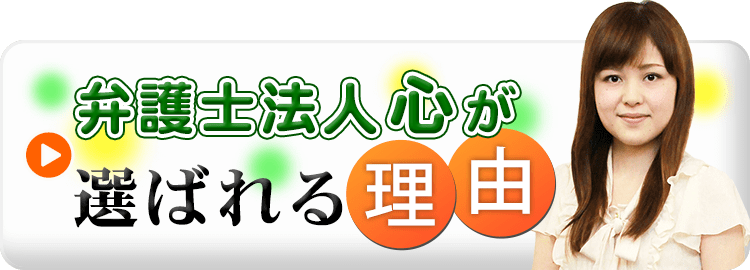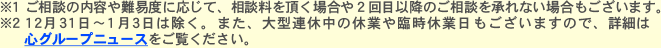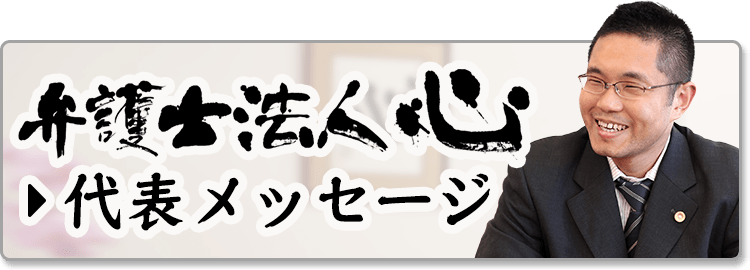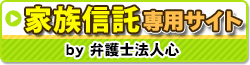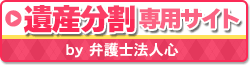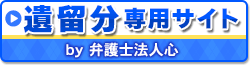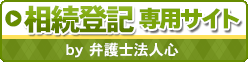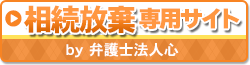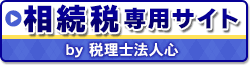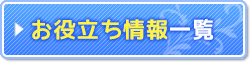遺言を作成しておいた方がよいケース
1 遺言がない場合はどうなるかを考える
ある人が遺言を作成せずに死亡した場合は、法律上定められた人に、定められた割合で、その亡くなった人の財産が相続されることになります。
例えば、Aが亡くなり、Aには妻Bと、CとDという子どもがいた場合を考えてみましょう。
この場合、亡くなったA(被相続人)には配偶者Bと子どもCとDがいるため、B、C、Dが法定相続人となります(民法887条1項、890条)。
Aが遺言を作成していない場合は法定相続分で分けますので、それぞれの法定相続分は、配偶者Bは1/2、子どもC、Dは残り1/2を等しく分け合い各1/4ずつとなります(民法900条1号、4号)。
参考リンク:国税庁・相続人の範囲と法定相続分
この分け方では不都合がある場合は、遺言を作成しておいた方がいいケースに当たります。
いくつか、具体例を挙げたいと思います。
2 法定相続分のとおりに財産を相続させたくない
例えば、1の例でAが病気のとき、Cはよく面倒を見てくれたが、Dは全く助けてくれなかったから、Cにたくさんお金を渡してあげたいとAが考えた場合です。
この場合は、BとCに各1/2ずつ相続させる旨の遺言を作成すれば、Dにはお金は残らず、Cに多くのお金を残すことができます。
ただし、このような遺言によって他の相続人の遺留分を侵害してしまっている場合は、侵害された相続人から遺留分を請求されてしまうなどの問題も生じやすいため注意が必要です。
3 法定相続人以外に自分の財産を残したい
例えば、Aに父親Eがいて、Eにも財産を残してあげたいと考えた場合です。
遺言がなければ、子どもがいるAの財産をEが相続することはできませんが、遺言で「Eに〇〇を相続させる」旨の意思表示をしておけば、EもAの財産を相続することができます。
父親に限らず、そもそも法定相続人がいない、友人に残したい、支援したい団体にお金を残したい場合なども同様です。
4 特定の財産を特定の人に相続させたい
例えば、Aが会社を経営していて、Cがその経営を受け継ぐことが決まっているが、会社の土地建物がA名義であった場合などです。
この場合、遺言がなければ、原則会社の土地建物はB、C、Dはそれぞれが相続分にしたがって、共有することになります(民法898条1項)。
そうなると、会社で使用する財産も引き継いだCだけではその土地建物の処分等が決められず、会社経営に関係のない者も含めた3人で話し合いをする必要があります。
そのような煩雑さを回避するためにも、遺言でCに会社に必要な財産を残すべきということになります。
他にも、家を妻に残したいなど、特定の財産を特定の人に残すことに意味がある場合などがこれに当たります。